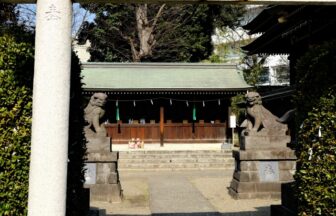私たちが日常何気なく使っている言葉の多くは、実は仏様の教えに由来しています。
日常に溶け込み当たり前に使っている言葉の、元々の意味やどのような仏教語に由来しているのかを簡単に解説します。
言葉の本来の意味、用法を知って頂く事で、小難しく感じる仏教用語に親しみを持って頂き、仏教の魅力に触れて頂ければと思います。
学生【がくしょう】
現在では、一般的に学生(がくせい)と呼び、特に大学で学業を修めている人を指します。
元々は〈学匠(がくしょう)〉〈学侶(がくりょ)〉ともいい、仏道を学習する僧、儒教などを学ぶ者を指し、大学寮の学生を意味していましたが、後に大寺で学ぶ僧も指すようになりました。
最澄(さいちょう)は、国の未来の為に大乗仏教の僧の養成が不可欠と考え、大乗の戒によって授戒し、学問・修行させる制度『山家(さんげ)学生式』を制定し朝廷に許可を求めましたが、残念ながら存命中には許可が降りず、没後7日目に許可され、翌年から大乗戒の制度が始まりました。
また,遣唐使に同行して往復する学問僧を還学生(げんがくしょう)、長く唐に留まって学問する僧を留学生(るがくしょう)と呼びました。
有名な還学生には最澄、留学生には空海が名を連ねます。
我慢【がまん】
煩悩の一つで、強い自我意識から生まれる慢心のことです。
仏教では、自分を固定的な実体とみて、それに執着することで起こる、自分を高く見て他を軽視する思い上がりの心を〈慢まん(māna)〉と呼び、このような心の状態を分析して、三慢、七慢、九慢と説きます。
我慢はこの七慢の中の一つです。
現在使われる、自分を抑制する、耐え忍ぶといった意味に使われるのは、我意を張る、強情の意味を介した転義で、近世後期からの用法です。
機嫌【きげん】
一般的には「機嫌が良い」など、その時の気分や感情を表現する言葉として用いられます。
元々は世間の謗り(そしり)、嫌われる事を意味します。
仏教では、その行為自体が罪悪であるものを戒める戒律を性戒(しょうかい)と呼び、それに対して、その行為自体は善でも悪でもないが、罪悪を誘発しやすい行為を戒める戒律を遮戒(しゃかい)と呼びます。例えば、財産の貯蓄や贅沢な物を持つ、というような事です。窃盗や妬みを誘発しやすい事例ですね。
そのような自他ともに罪悪を誘発しないように、自己を慎み、相手の気心を察するところから〈機〉をみる意味で〈機嫌〉と書きました。
さらに、相手の気心をうかがうことから「安否を問う」「ご機嫌うかがい」「気分が良い」などの気持ちを表す言葉として使われるようになりました。