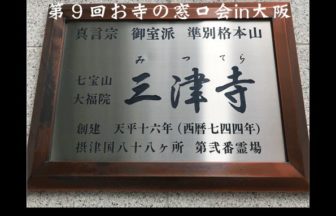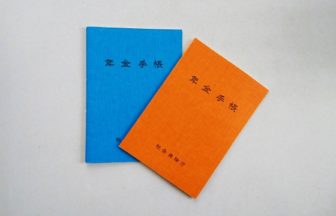私たちが日常何気なく使っている言葉の多くは、実は仏様の教えに由来しています。
日常に溶け込み当たり前に使っている言葉の、元々の意味やどのような仏教語に由来しているのかを簡単に解説します。
言葉の本来の意味、用法を知って頂く事で、小難しく感じる仏教用語に親しみを持って頂き、仏教の魅力に触れて頂ければと思います。
会釈
一般的には、人と人が行う軽い挨拶の意味で使われます。
元々は、お経の中の異なる意見を照合してすり合わせ、その教えの根本に立ち戻り、内容を矛盾なく説明する事の意味です。その意味が転じて、異なる意見の調和をはかる、相手と上手く調和する、対応するとなり、さらに転じて、軽い挨拶の意味になったとされます。
甘茶
アマチャというアジサイ科の落葉低木のアジサイの変種の若葉を、蒸して揉み、乾燥させ煎じた飲み物です。4月8日のお釈迦様の誕生日〈降誕会・花まつり〉に誕生仏に注ぐ行事に用いられます。
これはお釈迦様が誕生した時、天の神々が香湯を注いだという伝承に由来します。
挨拶
〈挨〉も〈拶〉も押す、迫るという意味があります。
宋代頃から見える口語表現で、群衆が他を押しのけて進む意味。禅では、相手の悟りの浅深をはかるために問答をしかけることの意味に用います。転じて、日本では応答・返礼などの意味に用いられ、また出会いや別れの時の親愛の言葉や動作のことを一般に〈挨拶〉というようになりました。