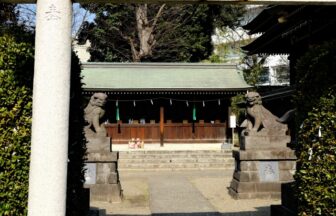私たちが日常何気なく使っている言葉の多くは、実は仏様の教えに由来しています。
日常に溶け込み当たり前に使っている言葉の、元々の意味やどのような仏教語に由来しているのかを簡単に解説します。
言葉の本来の意味、用法を知って頂く事で、小難しく感じる仏教用語に親しみを持って頂き、仏教の魅力に触れて頂ければと思います。
妄想
一般的には年少の男性、かつては特に商店での男性店員を指すことの多い呼称でした。
本来は、成人の僧を指す〈大僧〉の対で、年少の仏道修行者を指します。
同じ意味で青僧があり、青は未熟の意で、年も若くて経験の足りない僧のことを指します。
その反対が老僧で、老僧は必ずしも高齢の仏教修行者に用いる訳ではなく、修行を積んだ僧に対する尊称です。
工夫【くふう】
手段そのもの、あるいは手段を講ずるという意味で古くから用いられた言葉ですが、唐代には、手間ひまかけること、努力すること、さらには手間ひまかけるだけの時間的余裕を意味する俗語として用いられるようになりました。
禅宗では、主に参禅修行に励み、様々な努力を重ねるという意味で盛んに用いられるようになりました。