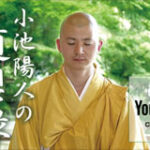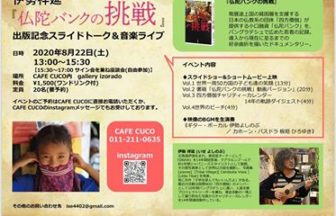私たちが日常何気なく使っている言葉の多くは、実は仏様の教えに由来しています。
日常に溶け込み当たり前に使っている言葉の、元々の意味やどのような仏教語に由来しているのかを簡単に解説します。
言葉の本来の意味、用法を知って頂く事で、小難しく感じる仏教用語に親しみを持って頂き、仏教の魅力に触れて頂ければと思います。
ありがとう
有る事が稀である、滅多に無い事、という言葉から「有り難し」「有り難い」と使われるようになったと言われます。
仏教に由来する言葉だとされ、経典でもしばしば使われます。
例、人間として存在する事は有り難い(難しい)、死すべき存在でありながら寿命がある事は有り難い(難しい)
この様に、私たちが日常で「当たり前」と思っていることも実は有り難い、稀な事であり、そこに感謝する事が大切だと説かれます。
うろうろ
道に迷ったり、どうして良いのか判断できずに困って彷徨っている様子を、一般的に「うろうろする」と表現します。
〈うろ〉とは漢字で〈有漏〉と書きます。
これは様々な心の汚れを表す総称です。煩悩と同じような意味と思って下さい。
サンスクリット語では有漏を[sāsrava(サースラヴァ)]と書き「流れ出る」ことを意味します。
私たちの六根(五感+意識)から煩悩が流れ出て、心が惑う状態を有漏と言いますが、それが重なり〈うろうろ〉と表現されるようになりました。
一方、流れ出る煩悩や汚れが無い状態を〈無漏(むろ)〉といいます。
ですので、あえて覚りに至った人を表現するなら〈むろむろ〉となります。
大げさ
一般的には、物事を実際より誇張する様子を表します。
仏教では、修行僧の正装で、三種類の袈裟のうちの最も大きい袈裟を指します。
その大きい袈裟の佇まいが威儀張ってものものしい所から、一般的な大げさという意味に転用されたと推測されます。