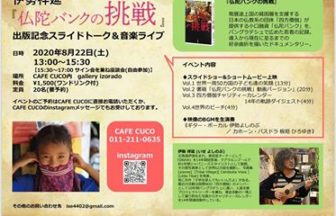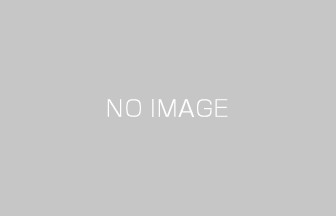★じつは身近な 仏教用語を3選ご紹介(さ行)★
日常何気なく使っている言葉の多くは、実は仏様の教えに由来しています。
日常に溶け込み当たり前に使っている言葉の、元々の意味やどのような仏教語に由来しているのかを簡単に解説します。
言葉の本来の意味、用法を知って頂く事で、小難しく感じる仏教用語に親しみを持って頂き、仏教の魅力に触れて頂ければいいなと思います。
砂糖
甘みを持つ調味料として家庭に浸透していますが、元々は沙糖と書き、8世紀奈良時代に日本に伝わった外来語の一つです。
サンスクリット語[śarkara(シャルカラ)]の訳語であり、沙は音写、糖は意訳なので、サンスクリット語と漢語の合成言葉です。
シャルカラは俗語に変化した後、ペルシャ語、アラビア語、中世ラテン語を経て、英語のsugarとなったので、sugarと日本語の砂糖はサンスクリット語という同一語源の言葉となります。
四苦八苦
「四苦八苦する」というと、現状がとても辛い状況、切羽詰まった様子を表す言葉で用いられます。
四苦八苦とは、人が生きる上で避けては通れない〈苦〉の種類を表しています。
まず、四苦とは生老病死です。
人は生まれる場所、条件を選べません。
人は必ず歳を取り老います。
そして病気にもなります。
やがて寿命がくれば死に至ります。
この四つが人間の根源的な苦しみであると説きます。
そして八苦とは、この四苦にさらに下記の四つを追加して八苦となります。
愛別離苦(あいべつりく)・怨憎会苦(おんぞうえく)・求不得苦(ぐふとっく)・五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四つです。
愛別離苦(あいべつりく)とは、大切な人や大好きな人であっても、いつかは離れなければならない苦しみ。
怨憎会苦(おんぞうえく)とは、逆に大嫌いな人、顔も見たくない人でも出会ってしまう苦しみ。
求不得苦(ぐふとっく)とは、求めるモノゴトが手に入らない苦しみ。
五蘊盛苦(ごうんじょうく)とは自分の心や、自分の身体すら思い通りにならない苦しみ。
仏教では、この四苦八苦は人間が生きている上で避けては通れない、根源的な〈苦〉として表します。
相続
一般的に「相続する」と言えば、跡目を継ぐことです。
相続権や遺産相続など、法律用語として用いられことが多いですが、元来は仏教語の転用であり、サンスクリット語[saṃtati(サンタティ)]または[saṃtāta(サンターナ)]の訳語です。人間の行為の連続性や因果関係の連続性を表し、本来は仏教哲学の用語です。しかし今日の相続という意味も連続性という意味は失われず相続しています。